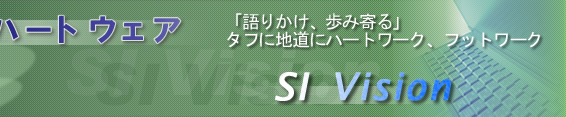『王政復古以来、すでに足掛け八年にもなる。下から見上げる諸般の制度は
追い追いとそなわりつつあったようであるが、一度大きく深い地滑りが社
会の底に起こって見ると、何度も何度も余りの振動が繰り返され、その影
響は各自の生活に浸って来ていた。こんな際に、西洋文物の輸入を機会と
して、種々雑多の外国人はその本国からも東洋植民地からも入り込みつつ
あった。・・・(中略)・・・ヨーロッパの文明はひとり日本の政治制度
に限らず、国民性それ自身をも滅亡せしめる危険なくして、はたして日本
の国内にひろめうるか、どうか。この問いに答えなければならなかったの
が日本人すべてであった。 当時はすでに民選議院建白の声を聞き、一方
には旧士族回復の主張も流れていた。目に見えない瓦解はまだ続いて、失
業した士族から、店の戸をおろした町人までが互いに必死の叫びを揚げて
いた。・・・(後略)・・・』
(第二部第十二章四から抜粋)
今回は、あの有名な「木曽路はすべて山の中である」の書き出しで始まる、島崎藤村の長編小説「夜明け前」第二部から上述の文章を採り上げた。ここには明治八年、御一新から八年を経過してもなお定まらない、年明け早々の日本混乱と人々の苦しみが書かれており、アジアの植民地からやって来る恫喝主導の外国人、理想に燃えてキリスト教文明を日本に植えつけようとする外国人、種々雑多、虎視眈々の外国人が入り乱れて、日本国内を撹拌している様子と、永い間の封建制度が崩壊して、そこに安住していた元は武士であろうと、名門の町人であろうと、流入してくるヨーロッパ文明に戸惑い、まるで大地震の後の余震のように、幾度となく揺さぶられる恐怖を抑えきれず、悲鳴を上げている様子が書かれている。この時期、歴史のうねりとしては、大久保利通と西郷隆盛が征韓論を巡って対立しており、西郷の一派は鹿児島に帰っていて、西南戦役の勃発寸前にあった。
藤村の「夜明け前」は、文庫本(岩波文庫)にすれば、四冊にもなる大作である。第一部は嘉永六年(1853年)の黒船来航から、徳川慶喜が大政奉還(1867年)をする辺りまでの上下巻二冊、第二部は明治元年(1868年)の江戸城明け渡しから、東北戦争を経て国家形成未完に苦悩する明治十九年(1886年)、物語の中では、主人公の青山半蔵が狂死するまでの上下巻二冊からなる。藤村がおよそ二十年に及ぶこの激動する日本を書き貫いた姿勢は、背景に日本の大きな歴史のうねりを描き、主人公青山半蔵が父吉左衛門から受け継いだ木曾街道十一宿の一つ馬籠宿の駅長としての生活と、若い時から学んで来た平田派国学を通して、更には半蔵が旅先の東京や京都で体感した事を通して、「下から歴史のうねりを見上げる」視点で捉え続けたことである。学んだ平田派国学が明治維新に寄与せず、半蔵が虚しさと寂しさの中で悲しい生涯を閉じるまでを、藤村は克明に追跡した。
日本版「戦争と平和」(トルストイ著)と評されるこの長編小説を、読まれてない方には先ず一読を、読まれた方には再読をしていただければと願う。明治という時代が現在日本の基盤になり得たのかという疑問、日本人の心情がどのように揺さぶられやすいのかという弱点を、時間はかかるが、二読、三読することをお勧めしたい。藤村が五十七歳から六十三歳という晩年に、昭和四年四月から昭和十年十月まで実に足掛け七年をかけて、木曾街道十一宿の一つ馬籠宿の駅長であった、父島崎正樹の生涯を丹念に調べあげ、在りし日の父を主人公青山半蔵に映して、明治日本の動乱の中で喘ぐ日本人の生きてきた様子を書いたのである。藤村も半蔵の四男和助として登場するが、和助にとっては祖父吉左衛門の友人である隣の伏見屋小竹金兵衛として登場する、大黒屋の十代目、大脇兵右衛門信興の三十巻に及ぶ「大黒屋日記」が、貴重な文献になったと安岡章太郎の解説にある。
話を物語に戻して、上述に掲げた文章前後の日本の歴史の流れと、青山半蔵の行動の軌跡を追ってみたい。藤村の言うように、「たとえ日本滅亡の悲劇が待ち受けていようと、この混乱を受け止め、解を見つけなければならないのは日本人すべて」であることには間違いなく、青山半蔵もそのように懸命に解を求めて動いた。平田派国学が縁で得た友人である中津川の蜂屋香蔵、浅見景蔵と共に、「御一新」という激動に立ち向かった。半蔵は馬籠宿の重職を果たしながらのことなので、香蔵や景蔵と同じような活躍が出来ずに悔やんでいたが、家族は半蔵が国学にのみ走るのを懼れた。半蔵は若者に学問を教えることで慰めていた。結局、幕府の解体は、半蔵が務めて来た馬籠宿の本陣、問屋、庄屋という仕組みだけでなく、山林問題も崩壊させることになった。「明治御一新の理想と現実」の現実を見ない者は躓いた。半蔵は家族に後を託して、新しい生き方を求めて東京に出た。
東京では国学を活かすべく教部省に勤めることになったが、当時の教部省では、あろうことか神官と僧侶を合同し、教導職に補任して広く国民の教化を行おうとした。神仏合同大教院を中央に設置、地方に中教院、小教院の建設を考案していた。青山半蔵の学んできた本居宣長から独立した平田篤胤などが唱える平田派の国学では、王政復古を中世における武士と混合する「建武中興における王政復古」ではなく、古代「神武天皇」まで遡って祭祀のしきたりを再構築するという純粋性を求め、「政教一致」を目標とした。「明治御一新」には半蔵が学んできた国学は通じなかった。幸いにも飛騨一ノ宮水無神社の宮司職を懇意の医者、金丸恭順から紹介され、飛騨に行く決心を固めていく。丁度そんな折に、明治帝の行列が神田橋見附跡を通過することを知って、この行幸を拝すべく半蔵も通りで待ちながら、若い帝が国学を平田鉄胤に師事したことを思い起こしていた。
通りで行幸を待つうちに、半蔵には先行きの不安感もあるにはあった。が、何といっても努めて学んだ平田派国学が新世に役立たなかった失望感、明治帝も一度は受講した平田派国学が現実の王政復古では空回りしている虚しさを認めざるを得ず、「これが御一新というものか」という内在していた憤りが熱い心となって表に出てきた。そんな思いを込めた歌を書いた扇を、行列の中にひょいと投げ込んだのである。扇に書かれていた歌は、「蟹の穴
防ぎとめずば 高堤 やがてゆくべき 時なからめや」と、「押し寄せるヨーロッパ文明の氾濫を子孫のためにも放任するときではないだろう」という意味が込められていた。民と共に苦難の道を歩む若い明治帝への思いが溢れての行動であったが、結果は「訴人が出た」と大騒ぎになって役人に取押えられてしまった。この事件があったのは明治七年十一月のことで、明けて八年一月中旬、贖罪金三円七十五銭の罰金刑で結審した。
冒頭に掲げた「王政復古以来、すでに八年にもなる。・・・」という文章は、丁度、献扇事件も罰金刑で済み、半蔵が東京を去る頃の様子を言っているのであるが、この辺から半蔵の生涯の歯車は段々と狂い始めて来るのである。明治帝を敬う心が世間では犯罪まがいに受け止められ、四年間の飛騨水無神社の宮司職を終え馬籠に帰ってみると、馬籠も新時代を迎えていて、心友、伏見屋小竹伊之助もすでになく、馬籠も若者の世代に移った。明治十三年に明治帝が東山道を御巡幸された時、馬籠宿を昼食場所に選ばれたが、周囲は半蔵を行列に近づけなかった。半蔵の酒量が多いと周囲から文句が出るようになった。五十六歳になった半蔵には辛い日々が続いた。やがてその虚しさが、祖先の作った万福寺への放火になって現れた。万福寺は障子を燃やしただけで大事に至らなかったが、半蔵には座敷牢が待っていた。「おてんとうさまを見ずに死ぬ」との言葉通り半蔵は死んだ。
「夜明け前」は藤村が用意周到の準備をして造り上げた著作であると思う。この執筆にかかる数年前、長男の楠雄を馬籠に帰農させたし、馬籠旧本陣跡の宅地購入もして、昭和元年には新居も出来上がり、二男の鶏二も帰した。藤村自身も何度か帰郷して執筆準備をしたのである。前述したように「夜明け前」を再読、三読されれば、正確な歴史のちりばめ方、物語の前後関係の気配りから、藤村のこの作品への思い込みの深さをその度に知らされることになる。
明治時代を日本の「夜明け前」と考え、この題名になったと思われるが、藤村がこれを書き上げた昭和初期も、次の時代、つまり「戦後平和日本の夜明け前」であったと言える。昭和十八年に逝った藤村は、日本敗戦の憂き目も、国民の苦渋も知らずに済んだ。軍事大国日本への藤村の確たる思いは知らないが、年譜で推測する限り「夜明け前」完成後には、顕著な活動をしなかった事が、却って良かったのではないか。
前段の応援団子の考えは、父の生涯を「夜明け前」として書いた藤村が、これを書きつつ『今もまた昭和の「夜明け前」なのだ』と思って筆を走らせていたのではないかとの発想から来ている。思うに、人は「明日を予想する」ことは出来ても「明日を知る」ことは出来ない。ある人間が、ある瞬間に、周囲から喜ばれ最大の賞賛を浴びたとしても、同じようなことが次の瞬間には、賞賛を贈った同じ人々から憎悪の罵倒を受け葬り去られることは有り得るし、賞賛を浴びた同じ人が、次の瞬間には、いわゆる「魔がさした」と言われるような、とんでもない悪事をすることも
有り得る。これが人間である。時の流れは一瞬たりとも止まらず、人の行動には「後悔しても後の祭り」とか、「今浦島に成り果てた」という言葉が常に用意されている。それほど人は常に不安定の中にあり、その不安定をもたらす源は、人間の内に生ずる止められない心の動きであり、心変わりにある。
人は、しばしば「自然に帰れ」、「原始に帰れ」、「明治に帰れ」、「原点に帰れ」などと、「帰ること」を口にして、過去を呼び戻そうとするが、過去と同じ場所に帰ることは不可能である。人は「帰るのではなく、過去から学んだものを持って新しい出発点に立つ」ことだけが許されているのではないか。つまり、人は常に「夜明け前」に立たされているのだと思う。いつ、いかなる時にも、次の瞬間のために、その時点で力んでもいない、平静な状態で、しかも「準備のできている最善の自分を置いておく」ということにならないか。そのことを熟知して「今を如何に生きるか」を考え、行動することが、私達に与えられている方法だと思う。(応援団A)
|