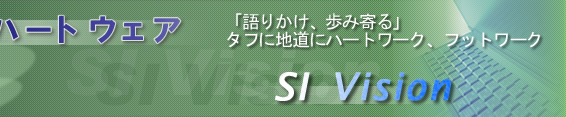角川文庫の千句からなる蕪村句集を読んでいくと、411番目で蕪村が59歳のときに詠んだ、「老いが恋わすれんとすればしぐれかな」という句に出会う。解説には「弟子の几董(きとう)が主催した発句会での出題による即興」との説明があり、この句のほかにも67歳になって、「秋の哀忘れんとすれば初しぐれ」と、前句を詠みかえたような句のあることが分る。また几董自身の「老いそめて恋も切なれ秋夕」の句があり、葉室麟著「恋しぐれ」の中でも、この句は蕪村を諌める句として使われている。今回ご紹介する「恋しぐれ」は、晩年の与謝蕪村や蕪村の弟子の恋の成否などを扱った一編、或いは弟子の波乱万丈なる人生の道程を辿った一編など、これら七つの短篇を集めた一冊である。
更に上述の句集解説を読み進めると、本書の三編目「隠れ鬼」に登場する弟子の大魯に宛てた蕪村の手紙が出てくる。その中で「老いが恋わすれんとすればしぐれかな」について、「しぐれの句は、一般的にはその風景を詠むことが多いが、恋の情景として詠まれることもある。ただ同じ恋の歌とはいえ、慈円の和歌とは少し意味が違う」とある。慈円の和歌とは「 我が恋は松を時雨の染めかねて真葛が原に風騒ぐなり 」(新古今和歌集)を指していて、その意は「松の緑は時雨にどれだけ濡れても色は変らないように、恋心だけは激しく騒ぐ」というものである。つまり、慈円の和歌からは「燃える恋心は、絶対に変わることはない」と言い切っている若さと激しさを感じる。
一方、「しぐれ」に己が心を託す蕪村の老いの恋は、「降ったと思えば止んでしまい、少し晴れ間が見えたかと思えば、また、しとしとと降り始める時雨と同じだ」と。つまり、断ち切ろうとして、一時は治まるかにみえても、またほつほつと燃え始め、その炎の勢いはたとえ弱くとも、心の奥でいつまでも消えないで燃え続けているものだという。この句集には、どの時期の気持ちを句にしたのかは不明ながら、ほかにも気がかりな恋の句が幾つかある。葉室麟はこうした句の一つひとつを吟味し、小説を組み立てていったに違いない。武士の矜持を書くことの多いこの作者が、老境、晩年の蕪村の恋心を書いたというだけで、葉室ファンの中には、これに飛びつく人もいるのではないか。
もう一つ、本題に入る前にお断りをしておきたい。今回は、「恋しぐれ」に収められた短篇の中から、蕪村の老いての恋にまつわる第一編の「夜半亭有情」と、最終編の「梅の影」を採り上げるが、先ずは「夜半亭有情」にある「夜半亭」の説明をしたい。夜半亭とは俳人集団の言わば屋号であり、最初に名乗ったのは、蕪村が20歳で故郷の大坂毛馬を出て、江戸で仕えた師匠の早野巴人である。夜半亭宋阿と言った。蕪村は夜半亭宋阿の内弟子となり、宰鳥とか、宰町という名前で句を作った。蕪村27歳のときに師匠宋阿が逝去、以後、京に上るまでの10年間は、下総結城はじめ関東、東北の地を遊歴していたが、詳細は掴めていない。「おくのほそ道」を辿った旅の記録はある。
宰鳥から蕪村へと変わったのは、下総結城時代の29歳のときで、放浪の後、嘗て夜半亭宋阿の元で一緒に句を詠んでいた、宋屋を頼って京都に居を構えた。蕪村は京都では俳句だけでなく絵画修業も重ね、越前、丹波にも足を運んだ。周囲からの勧めがあって、夜半亭二世を襲名したのは、55歳になってからである。葉室は「夜半亭有情」の中で、蕪村の年齢を67歳と設定しているので、歴史資料的な目で見ると、今は江戸俳諧の中興の祖の一人として、俳聖芭蕉と並び称せられる蕪村が、京の金福寺に芭蕉庵を落成させ、「洛東芭蕉庵再興記」を寄進して間もなくの頃に当たる。まさに最晩年の蕪村に焦点を合わせ、作者自身も還暦を迎えるという、年齢を意識しての作品であったのだと思う。
第一編「夜半亭有情」
この編は、職人風情の男が蕪村の家の様子を、じっと窺っているところから始まる。これに気づいた蕪村が、この男がどういう男であるのかを、訪ねてきていた友人の上田秋成(文筆家)や丸山応挙(画家)に尋ねると、応挙がさらさらと男の似顔絵を書き始め、蕪村が「その男です」と驚くと、この男は「染物屋の職人で、名前が与八である」ということまで知っていた。上田秋成が「それは怪しい。何か蕪村殿に恨みがあるのではないか」と言い始め、蕪村も気がかりになって来た。蕪村が一つ引け目に感じているとすれば、67歳という老境にいながら、ここ数年の間に芸妓の小糸を好きになっていることである。 蕪村一門の弟子たちも快く思っていないことを蕪村は 知っている。
ことの発端は、蕪村が出した句集「花桜帖」の中に、一門の弟子や馴染の京、大坂の芸妓たち、梅女、ことの、石松の句と一緒に、小糸の「いろいろの人見る花の山路かな」という句を、お披露目のつもりで載せたことに始まる。一門内での評判は悪く、特に大坂の梅女は「糸によるものならにくし凧(いかのぼり)」と詠んで、妬ましいことを師匠にあからさまにぶつけた。今回のこととは別としても、小糸のことを考えているうちに、蕪村はハッと思いつくことがあった。応挙に小糸の顔も描いてもらい、与八の顔が小糸に似ていることを確かめた。与八は小糸の父親か兄かで、蕪村を「年甲斐もなく若い小糸と」と蔑んでいるのではないか。嫌味の一つも言おうとしているのではないかと。
思案の挙句、蕪村は秋成と弟子の月渓の三人で、与八を尋ねていくことになった。与八の顔色は悪く労咳を患っていた。秋成は文筆家とは別に医者の顔も持っているので、病気の見舞いに来たと与八の家に上りこんだ。蕪村は思い切って、応挙が描いてくれた与八と小糸の似顔絵二枚を、与八の前に並べた。そして「これは応挙さんが描いてくれた絵だが、この女に覚えはないか」と尋ねた。与八は「私の顔に似ていますが、これは誰ですか」と聞き返した。蕪村は「この女は自分が祇園で馴染になっている小糸の顔だ」と答えた。与八は再度「蕪村先生はこの女がお好きなのですね」と尋ねた。蕪村は「好きなのだよ」と答えると、与八は両手で顔を覆ってしまった。与八は泣いているのだ。
ここから先の話は、読者が驚くほどミステリアスに展開していく。応援団子としては意地悪をする訳ではないが、書くのを止めることにする。どうぞ続きは本を読んで確かめていただきたい。蕪村が実際に過ごした生涯と、この小説で葉室麟が書く蕪村との違いは誰にも判らない。違いがあるとも、ないとも言えない。ただ、残されている句の中に、説得力を持つ句があるのも不思議だ。顛末のヒントにもならないが、蕪村が残した句で、この編の最終を飾る句「身にしむや亡き妻の櫛を閨に踏む」について言うと、これを蕪村が詠んだときは、蕪村の妻は健在であった。なのに「亡き妻」とはどうしてなのか。前出の句集解説には、「雨月物語『浅茅が宿』が下地か」との説明が、あることも付け加えておく。
ご案内のとおり、作者は「恋しぐれ」の中で随所に俳句を駆使しているが、第一編「夜半亭有情」の中では六つの俳句が出てくる。全てが蕪村の作品ではないが、その六つを並べてこの項は終えたい。参考までに前出の句集では「身にしむやなき妻のくしを閨に踏」として649番目に記されている。
「筆灌(そそ)ぐ応挙が鉢に氷哉(こほりかな)」 蕪村
「いろいろの花見る人の山路かな」 小糸
「糸によるものならにくし凧(いかのぼり)」 梅女
「花散りて身の下(した)闇(やみ)や檜の木笠」 蕪村
「鬼老いて河原(かはら)の院の月に泣く」 蕪村
「身にしむや亡き妻の櫛(くし)を閨(ねや)に踏む」 蕪村
第七編「梅が影」
最終編は、蕪村が亡くなったことを、大阪の芸妓梅女が初めて知ることになる場面から始まる。お梅(作者は梅のことを「お梅」と表現しているので、以後はお梅と書く)に教えたのは、同じ大坂に住み夜半亭一門の東葘(とうし)という、お梅のなじみ客の一人である。突然の師の訃報を聞いてお梅はうろたえた。東葘から師が金福寺の芭蕉庵に葬られるから、そのときにお参りに行けばよいと言われた。お梅はすぐに反論、師の家に出向いてお線香を上げたいと言ったが、東葘の戸惑ったような顔を見てドキリとした。自分も同じ夜半亭一門の弟子として、俳句の道に精進しているつもりでいるが、人は芸妓の遊びごとくらいにしか見ないのであろうか。胸の中に虚しさが湧いてきた。
東葘はお梅を贔屓にしたいという気持ちが以前からあったが、あるとき大魯から「梅女は私の弟子だ。邪な目で見るな」と罵られたことがあった。以後、東葘は大魯のことを妬み、ことあるごとに大魯の悪評を広めたこともある。蕪村は周辺の雑言には構わず、大魯にもお梅にも分け隔てなく弟子として遇した。そんな蕪村をお梅は慕って行くが、ある年に「みやこの春色いかに見過ごし給ふや」という手紙に付けて「花に来る人とは見えしはつ桜」という句を蕪村に送った。これに蕪村は「なには人の木や町にやどりしを訪ねて」という添え文とともに「花を踏みし草履も見えて朝寝哉」の句でお梅に応えたという。お梅の蕪村への気持ちは、師匠に対する思いを超えた慕情となっていった。
第一編のところでも、お梅の小糸に対する嫉妬の心が、「糸によるものならにくし凧」の句となったことは触れた。この句は意外な方に発展していって、これも蕪村の句友である暁台は、蕪村への手紙に「切ってやる心となれや凧」を書いて、小糸を切り離して上げた方が良いのではないかと諭してきた。蕪村は几董に「老い染めて恋も切なれ秋の暮」(前出の句集では「老い染めて恋も切なれ秋夕」と掲載)の句があって、師への諌めの句であることを蕪村も承知していた。結果的にはその後の蕪村は、小糸を諦めたような形となったので、お梅にすれば、師と小糸を別れさせた発端は自分の妬みにあると思い、何としても霊前に手を合わせてお詫びをしたいと願ったのである。
お梅は蕪村の家を訪ねあて、同じ弔問客に続いて入ると、奥の座敷に祭壇があるのが見え、近づいていった。座敷には蕪村の妻ともも、娘のくのも弔問を受けていた。手前には夜半亭の高弟たちも並んでいた。お梅の出現に眉をひそめた高弟たちは、焼香をせずにお梅が立ち去ることを望んだ。彼らの冷たい仕打ちに辛抱が出来なくなって、お梅もその場を去ろうとしたとき、絵の弟子で蕪村の家族と一緒に、一番近くで世話をしてきた月渓が「待ちなさい」と呼び止めて、ともとくのに「大坂の梅女さん」と紹介をして、師の仏前に手を合わすことができた。ただ、お梅には蕪村が遺族や香手たちに囲まれて、自分から遠い存在になってしまったような気持になって淋しさが増していった。
さて、第七編のここからの展開も、思わぬ方向に進んでいくのだが、ここから先はどうぞ本の中で確かめていただきたい。読者は「恋しぐれ」第四編の「月渓の恋」を読めばお分かりいただけるが、月渓は最愛の妻のおはるを船の遭難で亡くし、以後は蕪村のもとで絵の修業に励んだ。勿論、師の病床の側に月渓はいた。蕪村の辞世の句「白梅にあくる夜ばかりとなりにけり」は、師に命ぜられて、臨終の枕元で月渓が写した。師亡き後、月渓は「白梅屏風図」を完成させるが、作者は蕪村の辞世の句と月渓の「白梅屏風図」を、「梅の影」の中で結びつけたのである。そして、その屏風図完成のとき、月渓のすぐ傍にいて、絵の完成を共に喜んだのを、お梅としたのである。読者が胸を熱くする瞬間である。
この作品の中でも、作者葉室麟は多くの俳句を披露している。ここに順に記しておきたい。
「白梅にあくる夜ばかりとなりにけり」 蕪村
「花に来る人とはみえしはつ桜」 梅女
「花を踏みし草履も見えて朝寝哉」 蕪村
「老い染めて恋も切なれ秋の暮」 几董
「糸によるものならにくし凧(いかのぼり)」 梅女
「切ってやる心となれや凧(いかのぼり)」 暁台
「妹が垣根三味線草の花咲きぬ」 蕪村
「見苦しき畳の焦げや梅の影」 几董
「逃げ尻の光り気疎(けうと)き蛍かな」 蕪村
「明六ツと吠えて氷(こほ)るや鐘の声」 月渓
「八重葎(やえむぐら)君が木履(ぼくり)にかたつむり」 月渓
上述の句の中に「妹が垣根三味線草の花咲きぬ」があるが、 前出の句集の中でも 「妹が垣根さみせん草の花咲きぬ」として、769番目に出てくる。そして解説には「司馬相如の琴に喩えて、こちらは三味線で恋人に訴えよう」と戯れたこと。「小糸への恋心を示唆した自信作で、いかがなものかと門人の道立に示した」との注釈がある。このほか蕪村の句には気になる句として、59歳のときに句集に示した「花いばら故郷の道に似たるかな」と「愁ひつつ丘にのぼれば花いばら」がある。若い大坂毛馬時代を思い起こした気持ちを詠んだ句との推測もあるらしいが、応援団子には、棘が手足に触れたときの痛さが、何か蕪村の心の痛さを感じる「花いばら」の句である。それが気になる。
俳句の世界でも「虚」と「実」の兼ね合いは、 極めて難しい関係にある。 芭蕉が「虚」と「実」のことを「想像の世界を自由に遊びながら、究極のところでは物事の真実を表すように心がけよ」と言っているが、これを解釈すれば「ものごとの本質の把握を間違わなければ、偽りの姿も自由に使えばよし」ということか。では小説ならどうなのだろうか。蕪村の生涯も、その場その場の出来事も、これを全く正しく記述することは、出来る訳がない。作者はそれを百も承知の上で、作品の中で蕪村の家族、弟子たち、句友を見事に采配し、読者に本質を伝えたことになる。本書読後の爽快感、充実感は、作者が登場人物に注入した魂の気迫であり、それが読者に感動を与える。お薦めの一冊である。
(応援団子A)
参考文献
葉室 麟著「恋しぐれ」 (文春文庫) 2013年8月10日 第一刷
玉城司訳注「蕪村句集」 (角川ソフィア文庫) 2011年2月25日 初版
山下一海著「芭蕉百名言」(角川ソフィア文庫) 2010年5月25日 初版
|